第11話 瑠璃色の小包〜怪盗704号の午睡(後編)
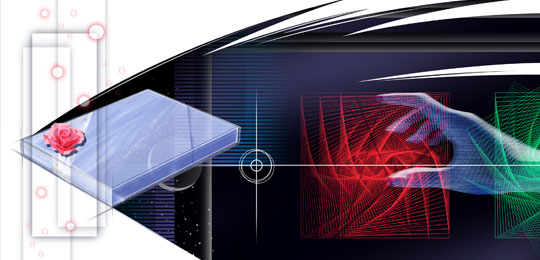
いつものように少し早い昼食を一階のカフェで取るため、白髪を櫛で梳かして外出の準備をしていた老婦人の耳に、入口のチャイムが鳴る音が響いた。珍しい、誰かしら、とゆっくりとした歩調で玄関に向かい、錆びた鉄製の扉を開ける。陽光を背に受けて、細身の青年が小包を片手に立っていた。上品に切りそろえられた口ひげと、帽子の下からのぞく蒼氷色の瞳がとても印象的だった。
「こんにちは。お届けものですよ、ご婦人」
涼しげな声でそう告げると、彼は抱えていた瑠璃色の小包を婦人に向かって差し出す。心当たりのなかった婦人は怪訝そうな表情を浮かべて彼から小包を受け取り、首を傾げながらおそるおそる包装をはがしていった。
「…まあ!」
婦人の目が大きく見開かれ、その手が小刻みに震える。「これは…娘の絵だわ!何ということでしょう!すみません配達員さん、一体誰がこの絵を…?」
「送り人は書かれていません」婦人を見つめ返し、彼はゆるりとした口調で返答する。「何か、良いお届けものだったようですね?」
「ええ…昔、画家を志して家を出て行った娘が、たった一枚、私宛に送ってくれた絵なの。でも、去年この家に泥棒が入って、その時にこの絵も盗まれてしまったわ。なのに…まさか、こんな奇跡があるなんて…ああ、今日は何て素晴らしい日でしょう…!」
歓喜の涙に頬を濡らす婦人に、彼は柔らかな微笑を浮かべながら、さえずりのように優しい声で「よかったですね、ご婦人」と答えた。
人目がないことを確認して足早に路地裏から建物に入り、階段を上って自室の扉をくぐった後、彼は天井に向けて大きく息を吐き、帽子をベッドの上に放り投げた。口ひげの端に手を当て、指でつかんで勢いよく横に引っ張る。粘着質な音と共に付け髭がはがれ、つやつやとした肌が現れた。洗面所で顔を洗い、乾いたタオルを片手に窓際の椅子に腰掛けると、手前の机に散乱した新聞を次々と手に取って素早く目を通していく。どの新聞にも盗難事件の情報は載っていなかった。恐らくツェッペリンの意向に従って、警察は捜査を打ち切ったのに違いない。計算通りだ、と彼はほくそ笑んだ。
警察側もツェッペリンも、一見失敗したかに見える今回の犯行の結末をさぞ不思議に思っていることだろう。しかしたとえ彼らが疑念を感じても、この犯行の裏に仕組まれたからくりには絶対に気付くまい。何故なら、
ツェッペリンが競売で大枚をはたいて落札し、自慢げに自邸に飾っていた『夜の微笑』が実は贋作で、今回贋作と称して持ち込まれた方の絵こそが本物の『夜の微笑』だった、ということを彼らは知らないし、もはやその真実を知る術を持たないのである。
レースのカーテンをそっと持ち上げ、隙間から向かい側の住宅を眺め見る。先ほどの婦人が、受け取った絵を居間の壁にいそいそと飾っている姿が確認できた。その微笑ましい光景に思わず彼は口元を緩める。
最初に婦人の部屋の壁に掛けられた絵の存在に気付いたのは、まだ彼がこの街を拠点に活動を始めて間もない頃だった。何気なしに眺めていた窓の外の景色に一瞬明らかな違和感を感じ、その原因に気付いて彼は大いに驚いた。「その行方も杳として知れず、幻の名画として名を馳せる『夜の微笑』が、まさかこんなところに?」にわかに湧き出る好奇心が行動に転化するまでいくらもかからなかった。翌日には彼は婦人の留守中に室内に忍び込み、間近で絵をじっくりと観察した。そしてその時、彼は目の前の絵が贋作であることに気付いたのである。しかし絵の出来はこれまで見たどんな贋作よりも精巧で、その技術力の高さに彼は思わず唸らされた。また、本来贋作としては押し殺すべき制作者の個性も、よくよく眺め見れば絵の端々にかすかに見て取れる。それらはいずれも未熟さを端に発したものではなく、制作者の持つ非常に高次の美的感覚が思わず滲み出たもので、結果的に絵の全体的な表現力を著しく向上させていた。この完成度はもはや真作をすら凌駕しているかも知れない、と彼は感じたものだ。
ひときわ興味をそそられた彼は、さらに翌日、アパートの管理人に変装して婦人の部屋を訪ねた。何気ない話題をいくつも持ちかけつつ部屋に上がり込み、自然を装いながら絵について問いかける。朗らかに答える婦人は、その絵が名画の贋作であることを知らないようだった。家を出た娘から届いたもので、だから多分娘の描いた絵だろうという。「どことなく昔、娘の描いていた絵の面影がありますし」そう話す婦人から勧められた暖かい紅茶を啜りながら、彼はおおよその事態を把握した。画家を志して都会へと旅立った婦人の娘は、何らかの事情で贋作の制作に手を染める羽目になったのだろう。どういった経緯でそのような事態を招いたのかを知る由はないが、才能ある身だからこそ、彼女は自分が目指した道と、置かれた現状とのギャップに悩み、苦しんだに違いない。贋作という仮面の隙間から顔をのぞかせている個性は、贋作作家に成り果てた人間が放つことの出来るものではない。もしかするとそれは、贋作との決別の意志の現れであったかも知れない、と彼は思った。だからこそ、彼女は最も近しい存在である婦人に、自身の決意を示すべくこの絵を送ったのではないだろうか…?
それ以来、たまに窓の外に目をやる時、壁の絵とそれを眺める婦人の姿を見るのが習慣になった。毎日、額にかすかに積もった埃を丁寧に拭き取り、愛おしげにその絵を扱う婦人の姿には、母の惜しみない愛を感じ取ることが出来た。
そんな日々に、半年ほど前に変化が訪れる。いつものように窓から婦人の部屋を眺めた彼は、ふといつもの壁に絵が掛かっていないことに気付いた。もうここ何年も、婦人が絵の場所を替えたことはない。不思議に思い、変装を施して再び彼女の住まいを訪れた彼は、意気消沈した婦人から、あの絵が盗難にあった事実を知った。目の下に隈をつくり、やや頬のこけた婦人の表情を見て、彼が決断を下すのにそれほど時間はかからなかった。取りかかっていた犯行計画を全て中断し、婦人の絵の行方の調査を始めたのである。
一ヶ月ほどでそのルートを解明することに彼は成功した。何とも驚いたことに、あの贋作は盗難の後、幾つかの穏やかでない組織や機関を経て『真作』として競売に出品され、大富豪ツェッペリンの元へと落札されていた。盗みの対象物が思いもよらぬ表舞台に上がってしまったことに彼は計画立案の多少の困難を思ったが、逆にこの事態が今回の一連の犯行計画に利用できると思いついたことで、一気に計画の構想が固まった。すぐさま彼は、計画に必要な最後の欠片、『夜の微笑』の真作を探すべく動き始めた。その所在を把握するのに三ヶ月の時間を要したものの、彼はついに闇市場の深部に沈み込んだ真作の在処を突き止め、その入手に成功した。そして計画は実行に移されることになったのである。
最終的に盗み出した絵を第三者である婦人に手渡すことになる以上、もし事件が公になれば、何の罪もない婦人にまで余計な火の粉が飛びかねない。そのような事態を避けるため、今回の犯行計画は普段よりも更にもう一段階、工夫を重ねる必要があった。ツェッペリンと親しい美術商を買収してしばらくの間僻地へ旅行に旅立たせ、その間にツェッペリンの邸宅に犯行予告を送りつける。間を置かず、美術商を装って彼の元に電話をかけ、それとなく話を持ちかけて彼の方から今回の犯行の件を相談させた上で、手元にある真作を贋作と称してツェッペリンの元へと届ける。そしてあとは警備員に変装して屋敷内に侵入し、絵の取り替えの実行日に犯行を行う。当日、警察が屋敷を訪れたことは捜査機関自体による目撃証言が成立するという点で彼にとっても都合が良かった。犯行後、残された絵が真作であることが判明すれば、その状況から彼らは「犯人が盗む絵を間違えた」と誤解することになり、すり替え作戦に成功したと勘違いしたツェッペリンは事件の立件そのものを取り下げるだろう。金にまかせて美術品を買い漁っているだけのツェッペリンに、元々自邸に飾られていた贋作と、手元に残った真作との細かな描写の違いなど見分けられるはずがない。真相が明らかにされる恐れはないと確信していたし、実際その計算には一寸の誤りもなかった。
こうして彼の計画は、今回もまた鮮やかに成功したのである。
柄でもなく人助けのような行為に及んでしまったせいか、婦人の笑顔を眺め見ているのが今は何となくこそばゆく思えた。彼は小さく苦笑し、カーテンを押し上げていた手を下ろして自室へと視線を戻す。両手を頭の後ろで組み、ゆっくりと目を閉じて椅子に座ったまま大きく伸びをした。窓から差し込む午後の日差しと心地よい疲労感が運んできた睡魔が、彼の体をゆるやかに支配していく。
一眠りしたら、中断していた仕事に戻ろう。
ぼんやりとそう考えながら、彼の意識は午睡のまどろみの中へと溶けていった。

 Previous
Previous