第15話 妖精の森
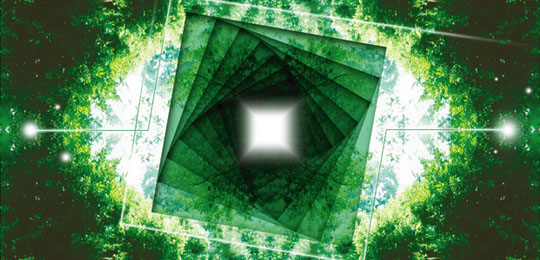
方角を見失って彷徨い始めてから、既に二日が過ぎようとしていた。
いくら辺りを見回せど、目にとまるのはただ緑、緑、緑。見上げると鬱蒼と天を覆う樹木の隙間から、か細い蜘蛛の糸のようにぶら下がった陽光が頼りなく揺らめいている。
カミュは苛立たしげに悪態をつき、前方の野太い幹を力任せに蹴りつけた。乾いた音が静まり返った緑のドームに響き渡る。
「妖精の棲む森」の噂は、探検家達の間では驚くほど古くから伝わっているものだった。しかし、それでいて妖精の存在の確たる証を示した者がこれまで誰一人として存在していないことからも、その森に関わることの難しさをはっきりと窺うことができた。未開の地を探索し、稀少な生物を捕らえて売り払うことを生業としてきたカミュにとって、自分の実力を世に知らしめるこれ以上のミッションはない。そしてこの仕事の成功は、自分の元への巨万の富を約束するものとなるだろう、と彼は確信していた。
先行きの見えない苛立ちをとりあえず鎮め、事を成し遂げた後の輝かしい将来を思い浮かべながら彼は再び探索を始める。ほのかに露を浮かせた雑草を踏みしめ、視界をさえぎる枝を両手でかき分けながら、歩みを進めていく。
そのとき、ふと視界の右隅に違和感を感じて、彼は立ち止まった。腰ほどの高さもないこんもりとした茂み。その葉の隙間から、ちらちらと光がのぞいている。緊張にほんの少し体を強ばらせて、彼はそっと茂みに近づき、胸元のナイフに手をかけながらもう片方の手で枝をそっと動かす。
そしてカミュは目を見張った。彼の親指ほどの大きさの、人の形をした生き物が、ぼんやりと光を放ちながら彼の方をじっと見上げていたのだ。妖精だ、彼は直感する。ナイフを握った手が一瞬行動を起こそうと動きかける。ここですぐに捕らえるべきだろうか?それとも、もし仲間がいるなら、皆まとめて…。
「これはめずらしい。迷い人ですか?もしお困りなら、女王様を訪ねるとよいでしょう」そんなカミュの思案にまるで気づかないかのように、目の前の妖精はのどかな口調で語りかける。一瞬でカミュは決断した。まだ仲間がいるのだ。こいつを騙して、行けるところまで行く方が良い。
「ええ、そうなのです。いたずら心を出して森に入り込んでしまったことを後悔しています。足は棒のようだし、お腹もぺこぺこです。是非、女王様の元へ案内して下さい」
「どうぞ喜んで。ただし、女王様の元へ行くには、このモグラの掘った穴をくぐらねばなりません。あなたの体では大きすぎる。私の魔法を分けてあげましょう」
そう言うと妖精はもごもごと何かつぶやく。瞬間、カミュの体が空気の抜けた風船のように勢いよく縮んでいった。同時に、妖精の体がむくむくと膨らみ、質量を増していく。
数秒後には、さっきまでと打って変わって、小人のカミュが大人並みの背丈の妖精を見上げる格好となった。
「あなたに魔法を分け与えたので、力が弱まったのか体が大きくなってしまいました。だが心配には及びません、じきにまた元に戻りますから。さあ、あなたは早くお行きなさい」そういって妖精はわずかに頬の上気した晴れ晴れしい顔でにっこりと笑いかける。
「申し訳ありません。ご好意に感謝します」お人好しな妖精の愚鈍さを心の中であざ笑いながらカミュはそう答え、地面にぽっかりと開いた穴に向かって勢いよく飛び降りた。
穴を抜けた先は、一面シロツメクサの草原だった。
普段はその姿に気も止めず単にその上を踏み歩くだけの存在だったシロツメクサも、今の小人状態のカミュにとっては一本一本が巨大な樹木と同様の威圧感をもって迫ってくる。ざっと見回した範囲に人影や集落のようなものはない。まだ先があるのか、と彼は苦々しげに舌打ちをして、乱暴な足取りでシロツメクサの森を駆け歩いた。しばらく進んでいると、かすかに水の流れる音が聞こえてくる。歩みを早め、草原を抜けると、目の前には深々と切れ込む谷があった。その遥か下方で川が流れているらしく、音はそこから聞こえてきているようだった。向こう岸は遠く彼方にある。道を誤ったか、と引き返しかけたその時。
「女王様に会いに行かれるのですね」
声の主はシロツメクサの花の上に腰掛けていた。その背中には、先ほどの妖精と異なり、虹色に透けた二枚の羽が生えている。
「この谷の向こうに女王様はいらっしゃいます。向こう岸へ渡らねば、女王様にはお目にかかれません」
「どうすればよいのですか?何か渡る方法があるのでしょう?是非、女王様に会わせて下さい」カミュはいかにも大げさな身振りで妖精に向かって頼み込む。
「簡単な事です。この羽があれば良い。貴方がお望みならば、私の羽を分けて差し上げましょう」そう言うと妖精はカミュの前へと降り立ち、羽の付け根に手をかける。痛々しい張りつめた音がして、羽は綺麗にもげた。彼がその二枚の羽をカミュの元へかざすと、みるみる内にカミュの背中に羽が現れる。
「さあ、この羽を使って谷を越えられると良い。大丈夫、私の羽はまたすぐに生えてくるのですから」
優雅な微笑みを絶やさぬまま、羽を失った妖精はそうささやく。まったくもって馬鹿な連中だ、とひそかに毒づきながら、カミュは爽やかな笑顔を浮かべて礼の言葉を述べ、谷を越えるべく飛び立った。
せせらぎの流れる谷を越え、眼下に広がる草原を眺めながら飛び続けていると、やがて視線の先に人工物らしき物影が確認できた。あれが女王のいる場所に違いない、そう考え、カミュは速度を上げて建物らしき影に近づこうとする。しかしいくら飛び続けても、一向にその影は大きさを増そうとしなかった。どういうことだ、と訝り始めた彼の後方で、大声で呼びかける声が聞こえた。振り向くと、先ほどとはまた別の妖精が、羽をせわしなく動かしながら近づいてくる。その頭部には、アンコウのような大きな触角が確認できた。
「そのままいくら飛んでいっても女王様の元へは行けないよ。あれは蜃気楼のようなものだからね」ようやくカミュの元に辿り着いたその妖精は、少々せわしない口調でそう捲し立てた。「女王様の元へ辿り着くには、この触角で方角を指し示してもらわにゃならないのさ」
「何と、そうなのですか。それで、貴方も他の皆様と同じく、その触角を私にお貸し頂けるのですか?もしそうならばとてもありがたい」
「ああ、良いとも良いとも。妖精にとって触角など髪や爪と同じようなもの、幾らでも再生するものだからね」
そういうと妖精は頭の触角の根元をつかんで勢いよく引きちぎり、カミュの頭に据え付けた。触角の切れ目と頭皮が触れ合った次の瞬間、触角は音もなく頭部と一体化していた。
「さあ行くがいい、女王の元へ。そしてその導きを受けると良い」
こころなしか居丈高になった感のある妖精の態度にかすかに違和感を覚えながら、カミュは言葉短かに礼を述べ、触角の指し示す方角へと向かい始めた。
厚い霧の壁を抜け、カミュはようやく建物の前へと降り立った。
ここが妖精の女王の…。
そう考えるやいなや、目の前の扉が重々しく開き、中から薄いヴェールに身を包んだ細身の女性が現れた。
「ようこそ、妖精の里の深部へ」
こだまして鳴り響く声に荘厳さがひしひしと感じられる。カミュは跪き、気づかれぬように右手を自分の胸元へと這わせながら、精一杯の笑顔で挨拶をしようと試みた。
「女王様、はじめまして。私は…」
「存じていますよ、カミュ。 貴方が邪な目的でこの森に足を踏み入れ、妖精達を騙して深部への立ち入りを図ろうとしていたことは、全て私の知るところです」
カミュは驚いて顔を上げる。女王は黙ったまま、ただ悠然と微笑み返す。
「ゆえに私は貴方に三人の刺客を差し向けました。貴方の胸元にはもはやナイフはない。確認してご覧なさい?」
慌てて彼は胸元をまさぐる。出てきたのは、一本の枯れた小枝だった。
「貴方はその利己的で暴力的な欲望ゆえに行く先を見誤りました。貴方の体は今や人間ではない。私たちと同じ、妖精となったのです。そして妖精となった貴方にとって、女王たる私の命令は絶対。もう貴方は、私の許しなしにこの里から出る事もかないません」
「何だって!?」
カミュは叫んだ。頭の中では混乱が大きな渦を巻いていたが、策に陥れたつもりの自分が実は策にかかっていた事実だけはかろうじて把握する事が出来た。そしてそれゆえに、どう解決のしようもない現状も。
「ああ、冗談じゃない、冗談じゃない!俺は嫌だ、こんな何もない牢獄のような場所で一生を過ごすなんて嫌だ!お願いだ、俺を元の世界に返してくれ!お願いだから、返してくれ!」
醜く取り乱すカミュと対照的に、女王の笑顔は煌めく刃のように鋭く、美しい。
「私も、望まぬ者を永久に里に幽閉しようとまでは、考えていません。貴方の行動次第では、いずれ貴方を元の世界に返して差し上げましょう。その条件を、聞きますか?」
「聞かせてくれ!何でも、何でもするから!」
彼女の目がすっと細まり、両頬と接する口元がゆるゆると持ち上がる。
「今後、貴方のように邪な目的で森に立ち入った人間を騙し、自分の力を分け与えて里の深部へと連れ込むのです。そう、ちょうど貴方がされたように。触角、羽、小人の魔力、この三つの力を無事に渡し終えた時、貴方は晴れて人間へと戻り、自由の身となるでしょう」
カミュはその内容を、呆然と聞いた。
あの、頬を上気させながら浮かべた、晴れ晴れとした笑顔は。
羽をもいだ痛みを感じぬかのような優雅な笑みは。
触角を渡し終えた後の、勝ち誇ったような表情は。
まさか。
「まさか…俺が出会った妖精達というのは…」
「そう、彼らも貴方と同じ。欲深く、情けを知らない罪人。貴方が一番最初に会った小人の人間は、今頃森を抜けて人間の世界へと逃げ帰っているでしょう。もう、今となっては彼の知る人々がこの世のどこにも生きていないことも知らずに…」
抑揚のない凍り付いた言葉が、容赦なくカミュの心臓に音を立てて突き刺さる。空はいつしか藍色の雲に覆われ、ざわざわと湿った風が彼の肌をぬるりと撫でて天へと舞い上がっていく。
「俺は…俺は一体いつ、戻れるのだ…?一体、いつになったら…」
「まだ二人、先約がいますからね」
震える膝をだらしなく床に打ち付け、絶望にうなだれるカミュ。
「幸い、妖精は時間から解放された存在。貴方が解放を望むなら、解放されるその時まで命尽きる事はありません」
ころころと鈴を鳴らしたような声で、女王は笑った。
「ゆるりと、待たれるがよろしいでしょう」

 Previous
Previous