第18話 空色の種
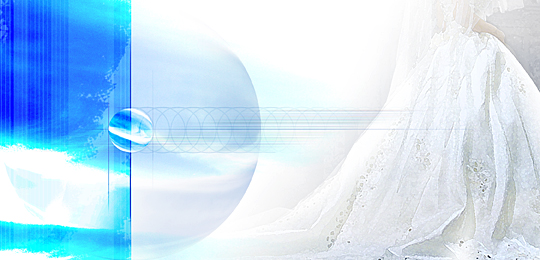
誰が言い出したことなのか、もう、はっきりとは覚えていない。
小学校の裏手に広がる、深く色濃い森。そのどこかに、手にした者に本当の幸せをもたらす「空色の種」がある…そんな噂話が、私の通っていた学校でまことしやかに囁かれていた。私自身を含め、探求心の豊かな多くの子ども達が意気揚々と空色の種の探索に出向いては、成果を得ることなく帰宅する日々を繰り返した。もっとも、私たちは欲深く目の色を変えて探し回ったわけではない。その当時の自分たちにとって、森へ飛び込んでやんちゃに暴れ回ることは、生きていく上でごく日常的で、かつ大切な生活の一部だった。「空色の種」探しも、そんな生活の延長線上のものとして自然に存在していたように思う。私はクラスで仲の良かった同級生と二人で連れ立って森に入ることが多かった。道中、引き抜いた背の高い雑草の茎を振り回しながら、あてのない種探しにのんびりといそしんだことが、今では懐かしく思い出される。見るもの全てが新鮮だった。その全身で感じる些細な体験全てが、さわやかな感動だった。
もう数十年も前の、懐かしい記憶である。
なぜ今、こんなことを思い出したんだろう…。
ぼんやりと考えを巡らせる私の横で、妻がそっと声をかけた。
「あなた、もうそろそろ、時間ですよ」
その声で私は我に返り、頭を上げる。
目の前でほんのりと輝く純白のドレスに、フォーカスが合った。
この世のものとは思えないような、透き通った笑顔にも。
そう、
今日は、娘の結婚式なのだ。
優しく添えられた娘の手を右腕に感じながら、
私はゆっくりと、歩みを進める。
鏡のごとく美しく磨き上げられた、ヴァージン・ロード。
正面、壁面にくりぬかれた十字架形の穴から、雲一つない晴天がのぞいていた。
その真下に立つタキシード姿の青年は、凛々しい表情で私達を見つめている。いつもよりもさらに、精悍で頼もしい面持ちだった。私は笑顔で彼の目を見つめ返し、わずかに顎を動かして頷く仕草を見せる。私が発した無言の挨拶に気付き、彼は表情を一層引き締めて深々と頭を下げた。
立ち止まり、横の娘に目を向ける。ヴェールごしに、彼女の目が潤んでいるのが見えた。涙もろいのは母親似のようだ。不安そうに見上げる彼女に、私は優しく微笑みかけ、小さく口を動かした。「行きなさい」と。
娘の視線がゆらりと揺れ、
やがて、正面の青年に、向けられた。
佇む私の横から、そっと、一歩を踏み出す。
右腕から、彼女の存在が、ゆるやかに剥がれていく。
一歩、また、一歩。
青年の腕にそっとその手をからめて、
視界に映る娘の姿は、少しずつ、遠くに離れていく。
突然、目にじんわりとした熱を感じて、
思わず、目元に手を当てた。
握りかけたその手のひらに、ぽとりと何かが落ちて滑り込むのを感じた。
涙ではない。
目元に当てた指を離し、手のひらを見つめる。
信じられなかった。
空色の種が、
そこにあった。
過去、いくら探しても見つけることの出来なかった、その種が。
私は知る。
幸せは、外にあるものではなく、
自分の中にこそ、見つけ出すことの出来るものだと。
そして、私は悟る。
何かを手に入れることに対してではなく、
自分の元から離れ、別たれていく存在、
その未来に向けて、想うことの出来る幸せこそが、
人の持つことのできる中で、もっとも貴く、美しい幸福なのだと。
静かに鳴り響く賛美歌にその身を包まれながら、
私は、ふと、
共に幸せを探し歩いた昔の友のことを思った。

 Previous
Previous