第20話 ネゴシエータ・ロボット
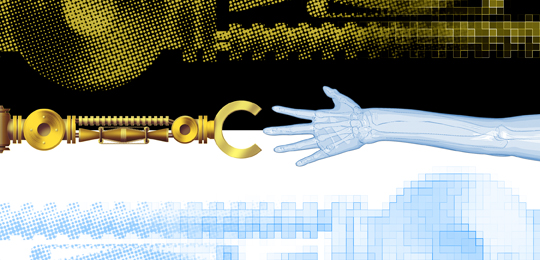
僕の会社の技術部には、サクライ君というとても優秀なスタッフがいる。
どんなに困難なプロジェクトに対しても、いつも冷静かつ客観的に問題点を抽出して解決法を探り出し、期待を大きく上回る成果を提案・具現化する。斬新な発想、柔軟な思考展開、迅速な成果構築など、業務遂行におけるどの点をとってみても、サクライ君の能力の高さは群を抜いていた。彼のような人間こそが、本当の意味でのエンジニア、そしてクリエータと呼ばれる人間なのだと、尊敬の念を込めて僕は思う。
ただ、そんな優秀な彼も、必ずしも万能な人間というわけではない。彼には一つ、決定的に苦手なことがあった。
第三者との一次的なコミュニケーションが、極端に不得手なのだ。
例えば日中、会社のデスクに座って黙々と作業しているサクライ君に何かの質問を投げ掛けてみても、その時彼から返ってくるのは、ああ、とか、うう、とかいった言語にならないうめき声だけで、まともに会話が出来るようなケースはまずあり得ない。とはいえ、それは彼の思考が瞬発性にかけている、というわけでは全くない。その証拠に、メールによって彼に届けられた質問への回答はいつも驚くほど俊敏、かつ質問意図に正確で、さらに問題解決のための発展的回答としての示唆までも大いに含んでいたりするのである。
要するに、彼は極端にシャイな性格なのだと、僕は思う。
そんなわけで、社のほとんどの人間が、サクライ君との業務のやり取りをもっぱらメールや書面で行っていた。僕の場合も、大半はそうだった。それでも、たまたま彼と背中合わせの席に座っていたこともあって、時々は、くるりと椅子を回転させて彼に向かって声をかけたりした。別に理由はない。単に気が向くまま、だったのだろうと思う。そのたびに彼は慌ただしくこちらを振り向き、くぐもったうめき声を聞かせてくれるのだけれど、一年に数回ぐらいは、ごく短い会話が成立することもあった。そんな時は、何ということもないことなのに、妙に嬉しい気分になったりしたものだ。
こんな日々にちょっとした変化が訪れたのは、桜も散りかけたある春先の日のことだ。
その日、出社したサクライ君の後方を、ひょろ長い二足歩行ロボットがぴったりついてくるのを見て、皆、びっくりした。
「私はサクライによって開発されたネゴシエータ・ロボットです。今後サクライに代わり、皆様と円滑にコミュニケーションを取り、また皆様からの言葉をサクライに伝達するべく、つくられました。よろしくお願いいたします」
ロボットはかしこまった挨拶の後、上半身をまっすぐ前方に折り曲げて丁寧なお辞儀をしてみせた。
一次的コミュニケーションを取れない現在の状況を、彼は僕らよりもはるかに深刻に悩んでいたのだということを、僕らはその時、初めて認識した。それにしても、よりによって何というエキセントリックな解答を用意するのだろう。こんな方法、サクライ君以外の誰一人として実行することは出来ないに違いない。才能もここまでくると凄まじいとしか、言いようがない。
サクライ君の開発したネゴシエータ・ロボットは、これまでの彼のエンジニアとしての成果の多分に漏れず、極めて高性能で、優秀だった。交わされる会話は本当にロボットかと疑うほどにスムーズで、質問に対する解答もまた、俊敏かつ明晰だった。サクライ君自身は黙々と自分のデスクで作業を続け、その周辺で社員とネゴシエータ・ロボットが忙しく会話しながら立ち回る風景が日常となった。僕は配置替えで別ブロックのデスクに移ることになり、以前のように彼と話をする機会は激減した。自身の業務をこなしつつ、パーティションの向こうから、ひとしきり人だかりの出来る彼のデスク付近を眺めていることが多くなった。
一年が過ぎ、二年が過ぎた。
サクライ君は会社に来ないことが多くなった。自宅で落ち着いて作業した方が効率良く業務を遂行できるから、との理由らしかった。一週間に一回の出勤日が一ヶ月に一回になり、半年に一回になり、やがて全く姿を見せなくなった。その彼の代理を務めるかのごとく、ネゴシエータ・ロボットは毎日会社に出勤し、多くの開発メンバーや会社の重役方とコミュニケーションをこなしていった。頭の固い上司達は、会社に顔を出さないサクライ君に対してぶつぶつと文句を言っていたりもしたようだけれど、業務への支障が少しも見られないことから、結局それらの不平はくすぶって消えていった。社員達もいつしかネゴシエータ・ロボットとコミュニケーションを計る日々を、ごく普通の日常として送るようになっていった。サクライ君本人のことを口にする社員が一人減り、二人減り、やがて彼本人の話題が会社でのぼることは、全くなくなった。
サクライ君の住むマンションで行方不明事件があったと報道された時も、そのニュースを心に留める社員は、誰もいなかった。
ただ一人、僕以外は。
今、サクライ君は一体どこでどうしているのだろうと、僕は時々考える。
彼が何を考え、
何を実践し、
その結果彼の身に何が起きて、
そしてどんな結末を迎えたのか。
いくつかの仮説を思い浮かべることは出来るけど、
それらの想像のうち、果たして何が正しいのか、その検証はきっともう出来ない。
どもりながら口を開いてたどたどしく言葉を連ねる彼の姿が、懐かしく思い出される。
もう一度彼と話をしたいな、と、そう思ったけれど、
そんな僕の自分勝手な気まぐれに彼を付き合わせるのも可哀想な話だな、と、思い直す。
多くは望まない。
ただ、彼が元気でいてくれるとよいな、と、
煌々と光を放つ液晶モニタを見つめながら、僕は一人静かに思いを馳せた。

 Previous
Previous