第17話 レインコート
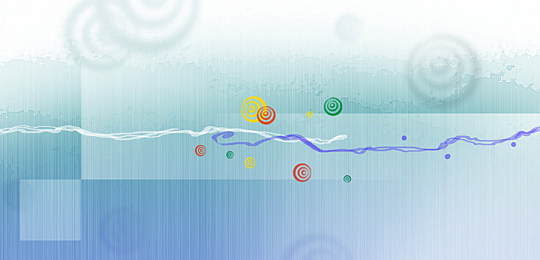
揺らめく、青。
繁る木の葉。灰色の雲。隙間からのぞく午後の空。それらが混ぜこぜに塗り込められた視界のキャンバス。そこに一滴、インクを落としたように仄かに混じった青の存在に、僕は水遊びの手を止め、顔を上げた。
昼下がりの公園である。通り雨が一時間ほど前にピークを過ぎて、今は粉のように細やかな雨粒が、時折ひんやりとした風に乗って顔をくすぐる程度だ。
視線の先、公園中央近くのイチョウの木の下に、鮮やかな青色のレインコートが見えた。おそらく僕と同い年ぐらいだろう、小柄な女の子がいた。
ゆるりと首を傾けた彼女と、一瞬、視線が合った。
その瞬間、両手にくっついた泥と砂が、急にそのざらついた感触を強めたように感じられた。僕は慌てて視線を逸らし、彼女に背を向けて足早にその場を立ち去る。ついさっきまで泥水を跳ね飛ばして水遊びに興じていた自分、そんな子供じみた僕の姿を、彼女が醒めた目で眺めていたような気がしてならなかった。そのことが何だか無性に悔しく、腹立たしくて、しっとりと湿った芝生の上を歩きながら、僕は思わず小声で毒づいた。
「何だい、この程度の小雨でレインコートなんて、お上品なこと」
夢を見たのは、その夜のことだ。
雲一つない空の下、僕は青いレインコートを身にまとい、広く深い水たまりの中へとダイブする。無限に広がるかのような透明の水の塊をしなやかに切り開き、幾筋も差し込む陽光の束を背に受けながら、水中の散歩を満喫する。泳ぐ僕の横を、小柄な魚の集団が軽やかに通り過ぎていった。彼らの体も、僕と同じく鮮やかな青色だ。綺麗な色だね、と僕は彼らに話しかける。彼らもにこやかに微笑んで、僕に向けて素敵な褒め言葉を投げかけてくれる…。
そこで、目が覚めた。
夢の記憶があまりにくっきりと残っていて、しばらくはただ呆然としていた。そのうち、何とも言えずおかしさがこみ上げてきた。
馬鹿だな、僕って。
悔しさも腹立たしさも、その原因は単純なことだった、と気づいた。
レインコートを羽織った彼女の姿が素敵だった。その姿が羨ましかった。ただ、それだけのことだった。
彼女への慎ましやかな好意の念を、無責任でわがままな悪態へとねじ曲げてしまった自分の精神的な幼さ。
「やれやれ…だなぁ」
吐息と一緒に小さく呟いて、僕は大きく寝返りを打った。暗い夜空を見上げながら、昼間の自分の態度を振り返る。
怒っているように見えたかも、知れないな。
そう思うと、彼女への申し訳なさがじんわりと込み上げてくる。だが、じめじめとした反省や後悔の念は、一瞬心をかすめた後、すぐに溶けて消えていった。もともと粘着質な性格ではない。悪いところは、直せば良い。まるでからかうような三日月の微笑をさえぎって、僕はゆっくり瞼を閉じた。
再び彼女に会ったのは、一週間後。雨の夕暮れだった。
先週と同じく、黄色く色づき始めたイチョウの木の下に、彼女は立っていた。落ち葉で華やいだ色彩を背景に、青いレインコートが一際映えて見える。僕の姿を見て、彼女がほんの少し視線を揺らせるのが確認できた。僕のことを覚えていたのだろう。舌でほんの少し口元を湿した後、僕はゆっくりとした動作で彼女の元へ近づいていった。
「先週も、会ったね」
「…うん」
「…あのさ」
ささやかな緊張が、全身をかすかに強ばらせる。
深呼吸。
息を整える。
「素敵な、レインコートだね」
言えた。
だが、彼女の表情は冴えない。
「どうしたの?」
耐えきれず、聞いてしまった。
「…あのね」 彼女は、おどおどとした口ぶりで切り出す。
「昔から、体があまり強くなくって。それでお母さんが、私が外に出る時は必ず、このレインコートを着せるようになったの。本当は…こんなもの、着たくないの。だって、とても変な、不自然な格好なんだもの。あなたみたいに、少しぐらいの小雨なんて気にせずに、そのままの姿で走り回っていたい。あなたが…羨ましい」
僕は驚いた。彼女が、自身の姿にそんなコンプレックスを持っているなんて、まるで考えもしなかったからだ。そしてすぐに思い至った。これはいわば、僕が彼女に抱いた気持ちの、そのまま裏返しなのだと。ならば。
「変なんかじゃないよ」
僕は、はきはきとした物言いでそう答えた。
そうさ。僕が彼女にかけるべき言葉は、決まっている。
彼女は目を丸くして、数回瞬きをした。
「本当に?」
「よく似合ってる。思わず羨ましくなっちゃうぐらい。だから…自分の今の姿、もっと自信を持っていいんじゃないかな」
彼女の表情に柔らかな安心感が吹き込まれるのが、見ていて分かった。
「ありがとう。そんな風に言ってもらえるの、初めて」
遠くで、彼女を呼ぶ声が聞こえた。
「また、一緒にお話しできる?」
「うん。いつでも」
その返事を聞いて、彼女は嬉しそうに微笑む。僕も、自然に出た笑顔を彼女に返す。胸の中は心地よい暖かさと清々しさで満ちていた。自分も、相手も、周り全てを幸せな気持ちに導くことができる、言葉には時折、そんな奇跡のような力が宿るものだ。
じゃあ、また、と言い残し、彼女は足早にその場を去った。レインコートから飛び出た栗色の尻尾が雨粒を弾いて元気に揺れている。
ふと、僕の名を呼びながら走り寄る人影が目に入った。ママだ。
「マロ、こんなところにいたの?駄目だよう、勝手にママの側から離れちゃ」
駆け寄ったママはそういって僕の頭をこつんと叩く。口ぶりに反して表情には笑顔がのぞいている。僕はぺろりと舌を出し、愛想よく一声、わんと鳴いてみせた。

 Previous
Previous