第19話 罪、罰、そして
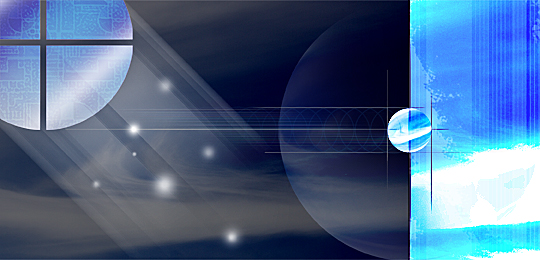
5年前、妻が死んだ。
自殺だった。
「奥さんの状態について、何かお気づきにはなりませんでしたか?」
ふらつきそうな体を二本の足で頼りなく支えながら、ただただ呆然と報告を聞く私に向かってそう質問する男の口調が、どこか非難めいて聞こえた。分かりませんでした、とかすれた声で答えたその時の相手の目に、一瞬、侮蔑の炎が灯ったように、感じられた。
当然の感想だと、そう思う。
なぜ、気付かなかったのだろう。
なぜ、何一つ見ることができなかったのだろう。
私は、医者だったのに。
人の命を救う使命を帯びた、人間だったというのに。
大学を卒業してから数十年、ずっと、前ばかりを見続けてきた。
大学病院での医療活動は、自分にとってこの上なくやり甲斐のある仕事だった。生涯を賭して前進し、より多くの人の命を救っていかねばならないと思い続けて、激務に挑み、過酷な日々を乗り越えてきた。
様々な場面に出会った。数えきれないほどの悲しみや哀しみにも、遭遇した。それでも、自分の意志が揺らぐことは全くなかった。一つ一つの経験全てが、命の重さと尊さを自分に再認識させ、心に一層の決意をみなぎらせていった。
全てがうまくいっていると、そう信じて疑わなかった。
とんだ偽善だ。
目の前に見える範囲だけではない、本当に無数の人々が、日々病に苦しみ、救いを求めている。そう頭で認識していながら、自分自身の周囲だけは、その例外であると、何の根拠もなく思い込んでいた。自分にとって一番近しい存在の異常一つ、気付くことができなかった。
お粗末としか、言いようがない。
誰がどう慰めてくれようとも、
自分が、彼女の命を奪ったも同然だと、そう、思った。
空が、藍から青へとゆるやかにその色彩を変えていく。
鳥の泣き声が、涼やかな夜明け前の風に乗って心地よく響いていく。
ほんのりとオレンジの灯の落ちたダイニングテーブルの上には、グラスに注がれたワインが置かれていた。先日、定年退職の記念に、同僚達がプレゼントしてくれたものだ。
私は薄暗い部屋の中、微動だにすることなく、椅子に腰掛けている。
視線は、ワイングラスの横に添え置かれた、一粒の錠剤に向けられている。
鮮やかなスカイブルーをまとった、球状の物体。
私を死へと誘う、旅立ちの薬だ。
その色彩を見て、ふと、私は古い記憶に思いを馳せる。
小学校時代に子どもたちの間で流行った、「空色の種」探し。幸せの象徴とされる「空色の種」を見つけ出すべく、親友と二人、野山に分け入って自然と戯れた日々。
ほんの少しだけ、頬がほころんだ。
自分にとって一番大切な存在を、自らの手で壊してしまった、罪。
許されざる罪に対する、罰。
その罰を遂行することが、彼女へのせめてもの償いであり、
自分にとって、望むべき幸せな人生の終焉なのだと、そう思った。
テーブルの上の錠剤を、そっと右手でつまみ、持ち上げる。
小さく口を開け、目を細めて、
薬を持つ指を、ゆるゆると、口元に引き寄せる。
白熱灯の光を受けて、種子が一瞬、ちかりと瞬いて揺れた。
粉塵が、
立ちこめていた。
瓦礫が、でたらめに作られた剣山のように、あちこちにとがって散らばっていた。
私はゆっくりと、目を開ける。
地獄に来た、と、そう思った。
この世の風景とは思えなかった。
焦点の定まらないまま、ぼんやりと辺りを見回す。壁は傾き、天井は捩れてゆがんでいる。家具はことごとく壊れ、木材とガラスの破片が周囲に散乱していた。
記憶が、徐々に鮮明になってきた。
あの時、頭上の白熱灯がぐらりと傾いて、
次の瞬間、天地を震わせるような爆発的な衝撃が、世界を襲ったこと。
頭を打ちつけた自分が、ほどなく気を失ったこと。
そして、
薄れゆく意識の中で、
思い出の中の妻が、私に向けて発した、言葉。
全身に滲む打撲の痛みに耐えながら、私はのろのろと体を起こす。
お菓子を包む銀紙のようにひしゃげたドアを無理やり押し開けて隣の部屋へと向かい、傾きかけた収納箪笥から銀色に光るアルミケースを引っ張り出した。蓋を開け、中身を確認する。薬瓶の幾つかが割れて中身が散乱していたものの、ガーゼや包帯など大半の道具は問題なく使用できそうだった。
多くの人々が、救いを求めている。
その命に向き合うことが、自分の果たすべき責務であり、使命だと思う。
今この時、自分が成すべきことは、一つしかないと、
そう感じる思いに、迷いはなかった。
妻の言葉を、受け止めようと思った。
かりにも医者ならば、
死によって幸せをもたらすような終焉を、決して望むなと。
そんな貴方の幸せなど、私は一片も望まないと。
一生、罪の意識を心に背負って、
死の直前まで、人の命と向き合えと、
そう私に投げかけた、言葉を。
ふつふつと沸き立つ決意を胸に、
外界から差し込む早朝の光を背に受けながら、
私は、静かに部屋を出る。
暗い部屋の中、円窓に縁取られて浮かぶその空の像が、
主のいなくなった部屋の中、一層青く、明るく白んでいった。

 Previous
Previous